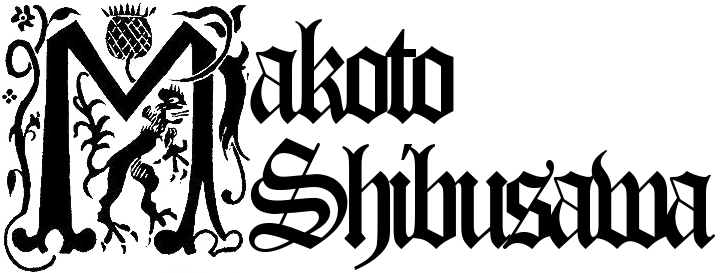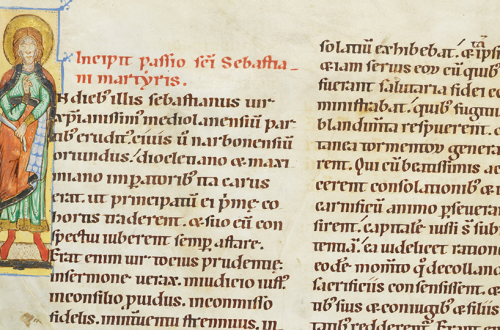美しい人には愛の囁きを
ご無沙汰しております。年をまたいでしまいました……もう2月ですが、本年もよろしくお願いいたします。
街はバレンタインデーに向けてハートのモチーフがそこかしこに踊り、ロマンティックな雰囲気です。今回はそんな季節にふさわしいテーマをいただきました(だいぶ前に頂いていたのですが、遅くなってごめんなさい)。
「中世人が、美人&イケメン(内面、外見を含む)を称える、口説こう(笑)とすると、なんと表現したのかな?!中世人にとっての褒め言葉、possibleWordとは!?」
※今回のご質問はFacebookでいただきました。匿名の方が気楽かと思いマシュマロで募集しておりましたが、このように各種SNSでお寄せいただいても構いません。
Q. 中世の人々は、どんな言葉で愛を囁いたの?
メッセージのやり取りの中でいただいたテーマでしたので補足しますと、現代の日本では美人を褒めるとき「かわいい」という言葉をよく使うけれど、西洋ではKAWAIIカルチャーが新鮮に受け止められるくらいになじみのない概念だったよね、という流れでいただいた疑問でした。
たしかに、よく子供に対して向けられる、未完成であったり、欠点も含めて愛おしいというような「かわいい」という感覚は、ヨーロッパでは稀薄であったようです。
中世の恋愛ということで、ドイツのミンネザングに見られる表現を見てみましょう。ミンネザングは貴婦人へと捧げられる愛の歌(この「貴婦人」は基本的に既婚なので、決して報われない愛)であり、女性の美しさを称える表現が多数出てきます。そう、大前提として女性は「美しいもの」なのですよね。端的に「美しい(schoen)」という形容詞も良く見られます。
次にあげるのは私の大好きなヴァルター・フォン・デル・フォーゲルヴァイデの作品の抜粋です。
Got het ir wengel hôhen flîz,(神は彼女の頬の細工に ひじょうな努力を傾けられた)
er streich sô tiure varwe dar,(神はとても高価な顔料をそこにお塗りになった)
sô reine rôt, sô reine wîz,(こんなにも清らかな紅色と白色を)
sô rôsenschîn, sô lilienvar.(こちらにはバラの紅を あちらにはユリの白を)
うっとりするような頬の美しさの表現ですね。このように、身体の一部に焦点を当て、その美しい色や形を褒めるという手法はよくとられました。先ほど抜粋した詩でも、頬だけでなく、頭や瞳、唇、手足などの美しさが歌われています。しかし、ここまで具体的に身体の部位を挙げて賞賛していくのは珍しく、一般的には褒める部位は瞳と唇に集中しており、それも「輝く瞳」や「赤い唇」といった形式的な表現が多かったといいます(賛美の言葉が形式的であったのは、この時代の語彙の乏しさによるものではありません。理想化された、完璧な女性の姿を描こうとすると、具体的な表現から遠ざかるという理由があったようです)。また、最後には具体的な裸体の描写が続くのですが、これはヴァルターに独特のもので、裸体の描写も当時の宮廷ではタブーと言えるものでした。あくまで崇高な、観念的な恋愛を歌おうとするミンネザングの中で、それでも目を奪われる肉体的な美しさについて零れ出るように称賛の言葉が生まれているのは面白い現象ですね。
肉体美は色によっても表現されました。先ほどの詩に出てくる紅色(rôt)と白色(wîz)はそのものが美しさを表す形容詞でもあります。
また、女性の美しさを讃える表現は、直接的に身体の部位を表すものだけではありません。比喩表現もよく見られます。ヴィーナスのような神話の存在に例えられたり、動物に例えられたりしました。動物による比喩表現の中でも特に多いのが鷹(ハイタカ)です。当時、鷹は婦人称賛の象徴的な存在でした。鷹は狩猟用であると同時に、宮廷人の愛玩用とされることもあった動物です。愛玩用には小さく攻撃性の少ないオスが好まれ、大きくて気性の荒いメスは鷹狩り用だったそうですが、その鷹が婦人の象徴として選ばれるあたりに、ミンネザングで描かれる婦人優位の奉仕的な愛の形が反映されていますね。
中世の人々というと、私たちと違うところばかりを探してしまいますが……愛しい人を見て、「なんて美しい」と素直にため息を漏らす。頭の天辺から爪先まで、その美しさを具体的に言い表そうとする。時には女神に、時には動物に例えて称賛する……こう書いてみると、意外と現代人と共通する感覚も持っていたのかもしれませんね。
A. 中世に独特の褒め言葉などはないが、瞳や唇といった造形の美しさを称えたり、その高貴さを鷹などに例えたりしていた
参考文献:
- 尾野照治著『中世ドイツ再発見』近代文芸社、一九九八年。
- 小野麻衣子「中世の恋愛叙事詩における鷹のモティーフ」『独文学報』一三(一九九七年)。
- 清水朗「ミンネザングの「愛」中世南仏・北仏浮情詩人との対比において」『言語文化 = Cultura philologica』三八(二〇〇一年)。
- 伊藤亮平・渡邊徳明編「中世文学における身体描写の逆説的レトリックを巡って」『日本独文学会研究叢書』一三三(二〇一八年)。
- 渡邊徳明「中高ドイツ語の宮廷叙事詩における愛の内面化について 」東北大学大学院文学研究科博士論文(二〇一五年)。