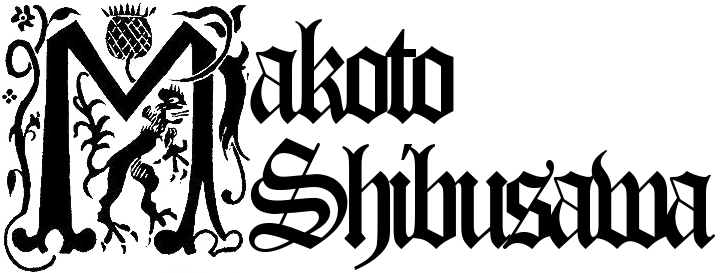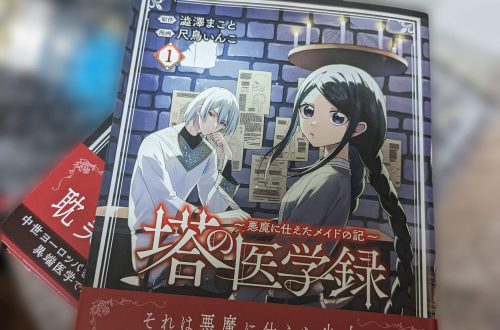民衆が口ずさんだメロディ
さっそくマシュマロをいただきました! ありがとうございます!
src=”https://www.makotoshibusawa.com/wp-content/uploads/2021/11/20613105676f5070547f4a2fd79cce2f.png” alt=”マシュマロ”
width=”597″ height=”910″ />
※お名前が含まれていたため、一応伏字にしてあります。
……なんて温かいメッセージでしょうか。嬉しくて何度も読み返してしまいました。
そして難しいご質問ですね。しっかり答えられるかはわかりませんが、頑張ります!
Q. 中世の教会音楽以外の音楽はどんな存在だったのか
ブリューゲルの絵を見に行かれたのですね。彼が生きた16世紀は一般的な時代区分としては近世にあたりますが、ルネサンスも宗教改革も突然変異的な事件ではありませんから、人々の宗教観は中世と地続きな部分も大いにあるとと考えてよいと思います。教会音楽以外の音楽を悪魔の音楽として貶めようとする試みは、中世からありました。
そう、教会音楽以外の音楽を、です。厳格に、規律正しくあろうとすることを考えると、音楽そのものを禁止しそうな気がしてしまいますが、音楽自体はキリスト教にとって重要な要素の一つでした。たとえば、聖書にはこんなみことばがあります。
ハレルヤ。主に新しい歌を歌え。聖徒の集まりで主への賛美を。(詩編149:1)
角笛を吹き鳴らして、神をほめたたえよ。十弦の琴と立琴をかなでて、神をほめたたえよ。タンバリンと踊りをもって、神をほめたたえよ。緒琴と笛とで、神をほめたたえよ。音の高いシンバルで、神をほめたたえよ。鳴り響くシンバルで、神をほめたたえよ。(詩編150:3-5)
これらは旧約聖書の詩編の言葉。キリスト教成立以前から、ユダヤ教徒の間で音楽が大切にされてきたことを示すものであり、つまりは、イエスも歌っていたということになります。音楽とは祈りであり、神を賛美するもの。歌うことも楽器を鳴らすことも、神に捧げる儀式のような側面があったのです。ですから、中世においても自由七科には音楽が入っていますし、グレゴリオ聖歌と教会旋法が成立したりと、知識人たちは音楽を探求し体系立てることに一生懸命でした。
しかしその一方で、中世における楽士(ミュージシャン)は賤民に分類される最底辺の存在でした。一見矛盾に思えるこの構造を理解するには、当時の人々の宇宙観を知る必要があります。
中世の人々にとって、世界とは二重構造でした。大宇宙(マクロコスモス)の中に、それと照応する小宇宙(ミクロコスモス)が存在する。小宇宙とは人間そのものであり、人間の生活に付随するものも小宇宙に属する存在として考えられる、という形です。阿部謹也著『中世賤民の宇宙 ヨーロッパ原点への旅』にわかりやすい説明があったので引用しましょう。
つまり小宇宙の内部は一応人間がある程度コントロールできる世界である。小宇宙である家の中にはカマドがある。カマドには大宇宙から持ってきた火が燃えているが、これは大宇宙の火を人間がコントロールしうる限りでそこに置いてあるわけで、コントロールできなくなれば火事になり家全体が大宇宙に戻ってしまう。
つまり、基本的には人間の生活空間、家を中心にして畑や都市という形で小宇宙が広がっているのですが、都市の中に存在していてもコントロール不能なものは大宇宙の存在として数えられるわけですね。綺麗な同心円型の二重構造ではなくて、小宇宙の中に紛れ込んでいる大宇宙の存在があり、よく見ると斑になっている、と言っても良いかもしれません。そして面白いことに、人間の中にも大宇宙の存在と考えられる人々がいました。それが賤民とされる人々です。彼らが「アウトサイダー」と称されるのは「(小宇宙の)外側の存在」だからと言えるでしょう。コントロール不能なものの代表格である「死」に携わる職業、刑吏や墓掘り人が賤視されたのはわかりやすい例ですね。
話を音楽に戻しましょう。今回いただいたマシュマロのメッセージの「音楽は、人間生活に、悲しみ、喜びの発露として、自然発生しちゃうものだと思う」……まさにその通りだと思います。自然のままに沸き起こる感情、そして思わず唇から溢れ出たメロディ。それは大宇宙から来たものと考えることができます。しかし一方で私たちは、感情も歌声もある程度コントロールすることが可能です。涙をこらえたり、怒りを抑えたりするのと同様、声を上げるのを我慢したり、逆に何の感情もなくても歌ったりすることもできる。私たちと音楽の関係性は、先ほど引用したカマドの例に近いと言えるでしょう。
すると、音楽を重視しながら民衆の音楽を敵視した理由も浮かび上がってきます。教会音楽や学問としての音楽は、本来危険な火を生活に活用するように「コントロールしうる限りでそこに置いて」いるのです。統制された教会音楽と自由な民衆音楽。教会からすれば、コントロールを失った火が家を道連れにして大宇宙に戻るのと同様、コントロールのきかない民衆音楽が信仰心を道連れにすることを恐れたのかもしれません。何しろ、キリスト教によって統制・統治されていた中世ですが、民衆がどこまで教化されていたのかは疑問です。教会が必死に否定しようとしても伝承や迷信は市井に溢れていましたから。
きっと彼らは、「コントロールされない」歌を、自由な気持ちで歌っていたのではないでしょうか。今よりも遥かに自由が少なく、娯楽もない時代です。音楽は、特に歌は、何を取り上げられても、自らの身体さえあればできるもの。この歌だけは奪わせてなるものかという情熱もあったことでしょう。ネウマ譜によって記録されたグレゴリオ聖歌などと違い、芸人(ジョングルール)たちの音楽は口伝だったので、民衆の音楽が一体どんなものだったのか、残念ながら現在知る術はありませんが、糾弾や排斥にもかかわらず決して消えることがなかったことは、「何度も」禁止されていることから明らかです。
どんな時に歌いたくなるかとのご質問もいただき、考えたのですが、私はきっと「息をしたいとき」に歌っています。これは息をするように自然に歌っているという比喩ではなくて、実際に呼吸がしたいという意味です。幼少期から喘息であったのと、かなりの緊張症だからだと思うのですが、整体の先生に「呼吸がへたくそ」と言われたりしていまして、そんな私が思い切り呼吸をする方法が歌うことなのかな、と思います。
当時の楽士たちにも、そうした側面はあったかもしれません。それも、私などよりもっと深刻で重大な。普段蔑まれ、文字通り息を潜めて生きている彼らにとって、心のままに音を奏で、人々に笑顔を向けられる瞬間は、何よりも息ができる=生きている瞬間だったのではないでしょうか。
A. 確かに規制されていたが、教会も権力者も歌いたいという民衆の心までは規制できなかった
参考文献:
- 金澤正剛著『中世音楽の精神史 グレゴリオ聖歌からルネサンス音楽へ』河出書房新社、二〇一五年。
- ジャン=クロード・シュミット著、松村剛訳『中世の身ぶり』みすず書房、一九九六年。
- C・メクゼーパー・Eシュラウト共編、瀬原義生監訳『ドイツ中世の日常生活 騎士・農民・都市民』刀水書房、一九九五年。
- アンドルー・マッコール著、鈴木利章・尾崎秀夫訳『中世の裏社会』人文書院、一九九四年。
- F・イルジーグラー・A・ラゾッタ著、藤代幸一訳『中世のアウトサイダーたち』白水社、一九九二年。
- アグネ・ジェラール著、池田健二訳『ヨーロッパ中世社会史事典』藤原書店、一九九一年。
- 阿部謹也著『中世賤民の宇宙 ヨーロッパ原点への旅』筑摩書房、一九八八年。
- 浜本隆志「中世ドイツの放浪芸人 (1)」『独逸文学』四四(二〇〇〇年)